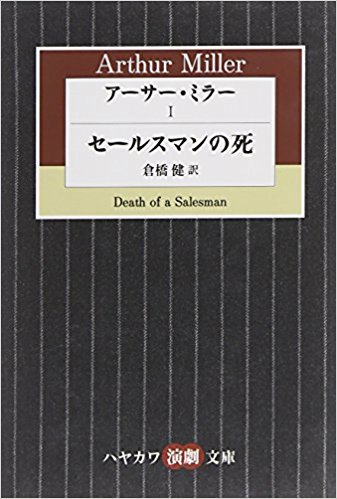幼な子われらに生まれ

モザイクに色分けされた画面。その上を、人の足が踏みつけてゆく。色分けされた地面は遊園地の入り口だ。父と娘が手をつなぎ入ってゆく。楽しげに遊ぶ二人。よくあるシチュエーションなので、離婚した父親が、別に暮らす娘と定期的に会う日だと分かる。それにしても仲がいい。メリーゴーラウンドの中で父親の信が聞く。
「もしお母さんに、新しい赤ちゃんが出来たらどうする?」
「私がハブられちゃうってこと? でも今のお父さんはそんな人じゃないから…」
実は信にも新たな家族がおり、妻の連れ子である二人の姉妹のほかに、新しい生命を授かろうとしている。だが信は新しい子どもを受け入れることに迷いがある。「そうでなくてもツギハギだらけの家族」なのに、今以上に複雑になることに怯えているのだ。

家に帰ると、赤ちゃんが生まれると知ってナーバスになった長女の薫が、あからさまに反抗して見せる。「こんな人、家族じゃない。本当のお父さんに会いたい」とまで言う。その本当のお父さんはDV夫で、自分も殴られ歯を折られたこともあったのに。どうしたらいいか分からない信は、次第に追い詰められてゆく…。
監督は「しあわせのパン」の三島有紀子。デビュー作の「しあわせのパン」はずいぶん素人くさい作品だなと感じたものだが、今回はずいぶん玄人くさい作品だと感じた。どちらも悪い印象ではない。三島はなぜこの作品を撮ろうと思ったのかと聞かれてこう答えている。
「…登場人物たちが本当に不器用で誰もが正解を見つけられずにいる、だからこそ魅力的だったし、子供も含めて全員が自分の中に住んでいる気がしました。…何より信が異質な人間(生命含む)と出会って、抑えていたものがひとつひとつ剥がされ本質が剥き出しにされていくのがおもしろいなあと思ったからです。」

信はもともとこの家族は「ツギハギだらけ」、他人の寄せ集めと考えている。家庭第一と考える男が、血のつながっていないことは最初から分かっていながら選択した道なのに、今更そんなことを言うのかと驚く。またその本音を笑顔のうちに隠しているところが、たちが悪い。薫の反抗はエスカレートしてゆくばかりだ。
信を演じるのは浅野忠信。この人の抱えるエネルギーの熱量は半端なものではない。薫に追い詰められた信は次第に余裕を失ってゆき、内包していた怒りが次第に前景化してゆく。その怒りは、信の怒りなのか俳優浅野忠信の怒りなのか、マグマのようにドロドロと熱せられて近寄りがたくなってしまう。
そんな時、元妻の友佳から連絡があり、今の夫がガンで余命いくばくもないと知らされる。別れ際の車の中で、有佳にこう言われる。
「理由は訊くくせに、気持ちは聞かないの、あなたって、昔から」

かつて信に黙って子供を堕したとき、激しい言い合いになったが、その時も同じだという。堕した理由は執拗に聞くが、堕ろす時の私の気持ちは聞かない―。しかし信にしてみれば、理由が分からないと気持ちが聞けない、のではないか。普通理由を聞くよな、と思いながら見ていたが、彼女の言いたいことは別にあることが終盤で分かる。
物語の終盤、薫のある行いに対して、理由を聞かずに気持ちを聞く信がいた。理由を聞かないのは、聞かなくても分かっているからだ。ということは、その人のことが分かっていれば、理由ではなく気持ちを聞くことになる。有佳はこう言いたいのだ。
「わかって」
そして信は、少しだけ父というものに近づく。

監督:三島有紀子
主演:浅野忠信、田中麗奈、宮藤官九郎、寺島しのぶ、南沙良
原作:「幼な子われらに生まれ」重松清著 幻冬舎文庫
日本映画 2017/ 127分
公式サイト
ギフト 僕がきみに残せるもの

カメラに向かって語りかける男。背後にベビーベッドが見える。
「6週間後 あのベッドに きみがやって来る
このビデオを撮るのは僕がどんな人間か きみ分かってもらうため
できるうちに たくさん僕の姿を残しておくためだ」
男は元アメリカンフットボールのスター選手。スティーヴ・グリーソン。引退後、筋萎縮性側索硬化症(ALS)と診断された。そしてその6週間後、妻ミシェルの妊娠が分かる。余命2~5年と言われる難病だ。もしかすると子どもに話しかけることが出来ないかもしれない。スティーヴは1日5分間、生まれてくる子どものために、ビデオメッセージを撮り続けることにした。それがこのドキュメンタリー映画の元になった。
スティーヴは少しずつ運動神経が損なわれてゆく。歩きがぎこちなくなり、食事が困難になる。やがて話すことも、呼吸をすることも出来なくなってゆく。友人二人は、その様子を介護のかたわら撮り続けていた。ここまで撮影するのかというくらい、その日常を撮り続け、おかげスティーヴが何に苦しみ喜び涙するのかが痛いほどよくわかることになった。撮影時間は1500時間。それをドキュメンタリー作家のクレイ・トゥイールが111分に編集した。

スティーヴは息子にリヴァース(川)という名前を付ける。
「川こそが火の源なんだ。火は木を燃料にして燃え、木を潤す水は川からくる。つまり川は火の燃料。僕という火にとって、君は川だ。」
普通は父親が息子の源だというイメージだが、スティーヴは息子が自分の源だという考え方をする。そして病気を自覚した彼は、これまでギクシャクとしていた自分の父親との関係を修復しようと試み始めるのだ。監督のクレイ・トゥイールは語っている。
「最初はこの映画は、主に悲劇的な環境で人生の目的を見つける男の物語になると思っていた。…僕が気づいていなかったのは、スティーヴと父親の関係で、その関係がスティーヴが彼の息子に残す教訓にも反映されていくところまで話が広がっていくということだった。世代を超えた父と息子の物語が現れて、驚かされた。」
スティーヴの父親はとても厳しい人だった。そして自分の考えを相手に押し付けようとする人らしい。映画では信仰を巡る父と子の対立が何度も描かれる。
「父さんの言うように信仰しないからこうなったと言いたいの?」
「そんなことはない。…まったく違う。」
そしてスティーヴはある時、泣きながら訴える。
「僕の心と神との関係を、無理に理解しようとしないでほしい」
泣くことも思うようにできないスティーヴが、それでも父親にすがって泣く姿が胸を打つ。ビデオメッセージでは、息子のリヴァースにこう語る。
「君はやがて僕と違う意見を持つようになる。それが楽しみだ。実際にそうなったらイラつくだろうけど。」

映画の終盤、スティーヴが父親に正面から問いかける場面がある。
「もしやり直せるなら、どういう父親になりたいの?」
「もっと優しい父親に…」
「もう十分優しいよ」
その時スティーヴが少し笑ったような顔をしていたのがとても印象的だ。
いよいよ人工呼吸器を装着しなければ呼吸がままならないとなった時、彼はなお生きる道を選ぶ。24時間介護が必要で、アメリカでは保険がきかず、5%の人しか選ばない道だ。しかしスティーヴのモットーは、「白旗は掲げない」ということだ。苦しみながらそれでも延命を選択する。その力の源は、息子。そして同時に父親ではないかと思う。父、自分、息子、世代を通じてその中を滔々と流れ続ける「川」がある。それが生命だ。
「僕がきみを愛するくらい、僕を愛して欲しいな。無理かな。でも、君の息子たちは同じくらい愛して欲しい。」

監督:クレイ・トゥイール
編集:クレイ・トゥイール、ブライアン・パルマー
撮影:タイ・ミントン=スモール、デヴィッド・リー
アメリカ 2016 / 111分
公式サイト
静かなる情熱 エミリ・ディキンスン

19世紀半ばのアメリカ。マサチューセッツ州の女子学校で、信仰を強要する教えに反発し、自らの心にのみ神を問う少女がいた。エミリ・ディキンスン。のちに現代アメリカを代表する詩人となる。
このひとは詩人だった
ごく普通の意味から
驚くべき感情を蒸留し
戸口に散る
平凡な種類の薔薇から
限りない芳香をひきだすのだ (J448)
エミリ・ディキンスンはやがて学校をやめ、アマストの実家に引きこもることになる。そして55歳で亡くなるまで、その家を離れることがなかった。女性に文学の仕事は出来ないと考えられていたこの時代、エミリは父親に許可をもらって詩を書き続ける。午前3時から夜が明けるまで。生前には10編しか公表されなかったが、死後こうして書かれた1800編もの詩が発見された。
私には名前がない あなたは?
あなたにも名前がないの?
同じね
黙っていてね 誰にも知られたくないから (J288)

監督はテレンス・デイヴィス。イギリスの映画監督である。映画製作の動機をこう語っている。
「詩とは崇高なものだ。彼女はアメリカの最も偉大な詩人であり、多くの人に読まれるべきだ。」
映画は詩へのオマージュに満ちているが、詩を生み出すエミリ自身の、生きる苦しみについてとても丹念に描いている。エミリは率直に思ったことを口にするが、それがいつも周囲との軋轢を引き起こす。子どものように辛辣で容赦がない。妹のヴィニーはエミリの辛辣さを非難してこう叫ぶ。
「あなたは崇高に人を批判しすぎるの!」
エミリは言い返す。
「では人間の品位はどうなるの?」
「品位も度が過ぎると無慈悲になるわ。・・・みんな人間なのよ。そのことを許してあげて」

エミリも分かってはいるが、言わずにはいられない。しかし自分が信じる「正しい言葉」は、他人には通じない。不愉快な思いをさせるだけだ。エミリは静かに家にこもり、何年もの間内面の何者かと対話を続けてきた。しかしその対話が普通の人間には通じないのだ。いや通じさせようともしていない。いわゆる嫌な人間になってしまっている。
魂は自分の社会を選び
そして戸を閉ざしてしまう
その神聖な仲間に
誰も加えてはならない (J303)
それが詩人であることの不幸なのだろうか。映画は端正な画面で、そうとしか生きられない人間の悲哀を描いて胸に迫る。エミリはこういう詩も書いている。人々に勇気を与えるものの孤独をうたって比類ない。
(前略)
極寒の地で わたしは「希望」の歌声を聞いた
まよい出た海の上でも聞こえた
「希望」は しかも困窮したときにも わたしに
パンくずひとつ ねだりはしなかった
 エミリ・ディキンスン(1830-1886)
エミリ・ディキンスン(1830-1886)
監督・脚本:テレンス・デイヴィス
主演:シンシア・ニクソン、ジェニファー・イーリー
イギリス・ベルギー 2016 / 125分
公式サイト
 「エミリー・ディキンスン詩集」KADOKAWA
「エミリー・ディキンスン詩集」KADOKAWA
彼女の人生は間違いじゃない

薄もやの桜並木の向こうからヘッドランプが近づいてくる。やがて車が現れると、防護服に身を包んだ人たちが降りてくる。原発関係の作業員のようだ。そこでカットが切り替わる。どこかの町の空撮。小さな部屋で目覚める女性。冷蔵庫から水を飲むと、炊けたばかりのご飯を小皿によそい、立てかけた写真の前に置く。
福島県いわき市。金沢みゆきは仮設住宅で父親と二人暮らし。母親を津波で亡くしている。みゆきは市役所に勤めているが、父親の修は補償金をつぎ込んでパチンコ漬けの毎日。修は酒を飲むと、秋田出身の母親をこの町に連れてきたことを悔やむ。
「俺と一緒にならなきゃ、秋田で幸せに暮らしていたはず…」
みゆきは土曜になるとバスで東京に出かける。見るともなく車窓をながめるみゆきの物憂げな表情。朝の美しい雲が広がる。いつまでも車窓を眺めつづける。東京でのみゆきはデリヘル嬢だ。なぜ?という疑問が映画を駆動させる。

監督は「さよなら歌舞伎町」の廣木隆一。みゆき役は瀧内公美。瀧内はインタビューでこう答えている。
「これであってるのか。正しいのか。自分でもわからない道を揺られながら向かっている。でも、東京から帰ってくるときは、これからもまた、こんなことを繰り返すのかな?と思っている。でも、自分は生きている。それを感じるバスの時間でした。女性として。人間として。バスに乗っている時間は、生きている自覚を持つ時間でした。」
パチンコで日々を過ごす人、原発の汚染水処理を仕事にして周囲から白い目で見られる夫婦、被災者に壺を売りつけようとする男…、出てくる人たちはマスメディアではほとんど取り上げられることのない被災者だ。どう捉えていいのかわからないのでメディアが目を留めない、「素」の人間。みゆきも表向きには、東京の英語学校に通っていることになっている。

みゆきは震災後に、それまで付き合っていた恋人と別れたらしい。
「こんな時、デートなんてしていていいのかな?」
と言った彼の一言で。
もしかするとみゆきは、生き残っている自分に負い目を感じていたのかもしれない。だからこそ自らを傷つけるためにデリヘル嬢になった。ならなければならなかった…。映画を観てそう思ったのだが、瀧内公美のインタビューを読んで、違うのかもしれないと感じた。
もう少しポジティブな感覚、生きることに貪欲な本能、強い生命力。瀧内はデリヘルについてこうも語っている。
「自分を傷つけるところもあるかもしれない。でも、傷つけるだけじゃなくて、何かを取り戻す、そういう仕事でもあるんですね。」

廣木隆一は飾りのない女性を描くのがうまい。「素」といえるような「女」。しかしなぜ?という問いの答えは誰にも分からない。だからみゆきの、何か思いつめるような表情をじっとみつめてしまう。監督も同じなのだろう。彼女を遠くからみつめ「君の人生は間違いじゃない」とつぶやく。そのつぶやきが映画を包み込んでいる。
物語の終盤、朝帰りしたみゆきが父親に「朝ごはん作ろうか」とたずねて米をとぎ始めるシーンがある。人生の何気ない習慣が、その人を救うかもしれない希望を感じさせる、とても美しい場面だと思う。米をとぐその音が、見終わっていつまでも心に落ちてくる。
監督:廣木隆一
主演:瀧内公美、高良健吾、柄本時生
原作:「彼女の人生は間違いじゃない」廣木隆一著 河出書房新社
日本映画 2017/ 119分
公式サイト
裁き

インド、ムンバイ。小さな部屋で子どもたちに地理を教えている白鬚の男。ナーラーヤン・カンブレ、65歳。時間が来ると町を横切って、イベント会場に向かう。そこではみなが待ちかねたように迎え、カンブレはステージに立って歌う。社会問題を訴える歌だ。とてもキレがいい。
♪ 大混乱の始まりだ
♪ 立て 反乱の時は来た
突然警察がやってきて、カンブレは逮捕される。しかし、この時歌った歌のせいではない、自殺ほう助の罪だという。彼の歌を聞いた下水清掃人が自殺したというのだ。裁判所で検事は、
“下水清掃人は下水道で窒息死しろ”
と彼が歌ったと主張する。否定するカンブレだが、目撃証人がいるらしい。理不尽な裁判劇が始まる…。

映画は裁判の進行にあわせて、検事、弁護士、裁判官それぞれの私生活を織り込みながら進む。監督は1987年ムンバイ生まれのチャイタニヤ・タームハネー。これが長編第一作。
「一番興味があったのは、裁判所における権威者、人の運命や時には生死を決める人たちも普通の人間であるということでした。それは、彼らの個人的な思想が裁判での決定に影響を及ぼしているということでもあります。もちろん、彼らも法律に従って仕事をしているのですが、解釈には彼らの個性が反映されてしまいます。それはすごく恐ろしいことだと思ったんです。」(ハフィントンポスト・インタビュー)
裁判が進むにつれ、証拠のいい加減さが次々に明らかになる。証人はプロの証言者で、いくつもの裁判で証言している男だし、下水清掃人はプロだからめったなことで事故は起きないとされていたが、実は満足な用具も与えられず、劣悪な環境で作業に従事していたことが分かる。
しかしいったい何のために、こんな嘘で逮捕されなければならないのか。結局は警察が逮捕したい、という人間を拘束するために、状況をねつ造しているだけなのだ。警察にはもちろん彼らなりの理由があり、カンブレは国家に害を加える人間と目されている。ただねつ造はねつ造だ。

しかも検事は検事でカンブレがどうなろうと知ったことではない。たんたんと有罪にするべく理由を語りつづけるだけだ。仲間の検事との会話では、同じ顔触れでもうあきたから早く20年で決まらないかな、などとうそぶく。そして休日にはよそ者を排斥する芝居を家族で楽しむ。それが「人の運命や時には生死を決める人たち」の姿なのだ。監督はこうも語っている。
「裁判所の所長や検事も市井の人間となんら変わらないのですが、だからこそ裁判所で見られる欠点は、ある種社会の欠点の反映なのではないかと考えたのです。」
見ていてインドの問題でありながら、日本の国会の状況を髣髴とさせるものがある。嘘や言い逃れがはびこり、事実に対するリスペクトがない。事実を大切にしない社会で私たちは安心して暮らすことは出来ない。「人の運命や時には生死を決める人たち」が恣意的にふるまって平気な社会は恐ろしい。

カンブレはこの先どうなるのだろうか。しかしこの男は淡々として動じない。このような社会に慣れてしまっているのか。ねつ造に慣れるというのもまた恐ろしく、淡々とした演出がそのことを静かにあぶりだす。
監督・脚本:チャイタニヤ・タームハネー
主演:ヴィーラー・サーティダル
原題:COURT
インド映画 2014 / 116分
公式サイト
ハクソー・リッジ

アメリカ・ヴァージニア州。野山を駆け巡る2人の少年。仲のいい兄弟。20世紀初めの情景。飲んだくれの父親の前で取っ組み合いのケンカ。止める母親。少年デズモンドは落ちていたレンガで弟を殴ってしまう。気を失い倒れこむ弟。「死んでしまうかもしれない…」自分がしたことにショックを受けたデズモンドは、部屋に飾られていた「汝殺すなかれ」の文字を呆然と見つめ続ける。
成長したデズモンドは、日本の真珠湾攻撃に衝撃を受け、陸軍に志願する。しかし、訓練の際、「信仰のため武器に触れることは出来ない」と銃を取ることを拒否したことから、上官や仲間から様々な嫌がらせを受ける。
「自分は武器を持たずに衛生兵として戦場に行き、仲間を救いたい」
そう主張するが、上官は「銃を取らない人間は信用できない」と除隊を宣告する…。

これは沖縄戦で武器を持たずに最前線に赴き、衛生兵として75人の負傷兵を救助した実在の人物の物語だ。監督は10年ぶりにメガホンをとった「ブレイブハート」のメル・ギブソン。
「デズモンドは自らの主義と信仰に反するものとして、暴力を忌み嫌っていた。だが彼は、第二次世界大戦において衛生兵として祖国に奉仕したいと考えていた。最悪の戦場に武器も持たずに赴こうだなんて、いったい誰が考えるだろう?そのことが、僕の心をとらえて放さない。」
実在するデズモンド・ドスは1950年、“良心的兵役拒否者”として最初の名誉勲章を授かった。映画化の話はそのころからあったが、実現までに50年以上を要した。デズモンドが静かな生活を送ることを選んだからだという。

見ていて分かりづらいとすれば、デズモンドが“良心的兵役拒否者”にあたるということだろう。彼は兵役を拒否しているわけではない。むしろ志願しているのだ。しかし銃を取ることは拒否した。つまり戦争には参加したいが、戦うことは拒否したい、というのだ。上官が「?」となるのも無理はない。
デズモンドはどんなに過酷な目に会っても、「汝殺すなかれ」の信念を曲げなかった。しかし、それほど強い信念があるなら戦争そのものに反対した方がいいのでは、とも思ってしまう。このあたり、人にはそれぞれ役割があるとしか言いようがない。
おそらく彼の認識の中では、戦わなければより多くの同胞が敵に殺される。そのため戦争は避けることは出来ないし、敵を殺さなければならない。自分もその行為に参加しなければならない。しかし殺す役目は自分ではない、ということなのだろう。

戦争を肯定しながら戦いを否定する、というアクロバットを成し遂げるために、デズモンドは死を恐れず、獅子奮迅の活躍で仲間を救出し続けるしかなかった。いやそれほど難しい話ではないのかもしれない。常に自分に出来ることは何かを問い、どのような場面にあってもその答えを実行し続けた、ひとりの男の物語なのだ。
デズモンドを徹底的にしごく軍曹の役を演じたヴィンス・ヴォーンの言葉が、この映画の核心をついている。
「デズモンドは自分自身に正直に生き、信念を貫き通そうとしていた。もし誰かが、自分の信念に基づいた行動をして、その結果を潔く受け入れようという態度を見せたとしたら、その人物を尊敬せずにはいられないはずだ。」
監督:メル・ギブソン
主演:アンドリュー・ガーフィールド、テリーサ・パーマー、ヴィンス・ヴォーン
アメリカ。オーストラリア 2016 / 139分
公式サイト
セールスマン

暗闇にうかびあがるベッド。照明を移動させる音。次にソファ。そして正面に派手なネオン看板。これは演劇の舞台だ。しかし人はいない。
一転して叫び声。ドヤドヤと階段を駆け下る音。アパートが倒壊しそうだという。これは現実だ。主人公らしき男が、助けの必要な隣人を抱えて降りてゆく。窓にひびが入る。外にはブルドーザーがうなりをあげている。
イランの首都テヘラン。乱開発のひずみで住む場所を失ったエマッドと妻のラナは、ともに舞台俳優だ。稽古中の舞台はアメリカの劇作家アーサー・ミラーの「セールスマンの死」。劇団仲間が紹介してくれたアパートに急いで引っ越した二人だったが、ある夜、ラナは呼び鈴を夫のものと勘違いし、見知らぬ他人にドアを開けてしまう…。
監督・脚本は「別離」が世界的にヒットした、イランのアスガ―・ファルハディ。
「私は学生の時に、「セールスマンの死」を読み、とても胸を打たれました。…とても重要なポイントは、都会であるアメリカの突然の変化によって、ある社会階級が崩壊していく時代の社会批判です。急速な近代化に適応できない人々が崩壊するのです。その意味で、この戯曲は、私の国イランの現在の状況をうまく捉えています。」

映画を観た後、パンフレットに並べて売られていた「セールスマンの死」の文庫本を買って読んでみた。筋として共通する部分はほとんどないと言っていい。落ちぶれた老セールスマンが、期待をかけた息子ともうまくいかず、起死回生で保険金目当てに自死するという悲劇だ。敗残の人間に厳しいアメリカ社会、自己欺瞞と欲、父と子、様々なテーマが折り重なって考えさせられる。しかし映画は「急速な近代化に適応できない人々が崩壊する」話ではない。
映画のラナはその夜に闖入した何者かによって乱暴されケガを負う。エマッドは怒り、警察に行こうというが、精神的にも憔悴したラマは事件を表ざたにしたくないと拒む。しかしエマッドの怒りは収まらない。傍にいて欲しいというラマをひとり置いてまで、犯人を見つけ出そうと捜索を始める。その果てに彼が見つけ出したのは意外な人物だった…。

だが映画のタイトルは「セールスマン」なのだ。「セールスマンの死」のモチーフが映画の中に潜んでいるに違いない。それはいったい何なのだろう。
映画の中で稽古として紹介される「セールスマンの死」のシーンがある。老セールスマンが若かりし頃、浮気現場を息子に見られる決定的な場面だ。以来、息子に対する負い目が消えず、それに比例するように過大な期待を寄せ、結果として息子をダメにしてゆく、その発端の事件である。老セールスマンが泊まっていたホテルを訪ねてきた息子。その時、見えない浴室から聞こえてくる女の笑い声。これが映画では後半への微妙な伏線になっている。
そして両者に伏在するのは人間の「プライド」の扱いがたさだ。老セールスマンは羽振りが良かった過去のプライドから自己欺瞞に陥り、現実を見ようとしなくなる。またエマッドは隣人たちの視線を気にして、プライドを保つために復讐せずにはいられなくなる。どちらもそのことが周囲(家族)に軋轢をもたらし、遂に破滅へと至る。

人は己の心に潜む、何か虫のようなものに縛られずにはいない生き物なのだ。それは時にプライドであり、時に憎しみであり、時に欲望であったりする。後悔はするがまた同じ虫がうごめくと同じ結果をもたらす。夫婦であっても、家族の中にいても、虫に対処するのは結局自分しかいない。虫は自分自身だから。その意味でどんなに孤独にみえなくても、人は孤独である。
監督・脚本:アスガー・ファルハディ
主演:シャハブ・ホセイニ、タラネ・アリドゥスティ
イラン・フランス 2016 / 124分
公式サイト