セールスマン

暗闇にうかびあがるベッド。照明を移動させる音。次にソファ。そして正面に派手なネオン看板。これは演劇の舞台だ。しかし人はいない。
一転して叫び声。ドヤドヤと階段を駆け下る音。アパートが倒壊しそうだという。これは現実だ。主人公らしき男が、助けの必要な隣人を抱えて降りてゆく。窓にひびが入る。外にはブルドーザーがうなりをあげている。
イランの首都テヘラン。乱開発のひずみで住む場所を失ったエマッドと妻のラナは、ともに舞台俳優だ。稽古中の舞台はアメリカの劇作家アーサー・ミラーの「セールスマンの死」。劇団仲間が紹介してくれたアパートに急いで引っ越した二人だったが、ある夜、ラナは呼び鈴を夫のものと勘違いし、見知らぬ他人にドアを開けてしまう…。
監督・脚本は「別離」が世界的にヒットした、イランのアスガ―・ファルハディ。
「私は学生の時に、「セールスマンの死」を読み、とても胸を打たれました。…とても重要なポイントは、都会であるアメリカの突然の変化によって、ある社会階級が崩壊していく時代の社会批判です。急速な近代化に適応できない人々が崩壊するのです。その意味で、この戯曲は、私の国イランの現在の状況をうまく捉えています。」

映画を観た後、パンフレットに並べて売られていた「セールスマンの死」の文庫本を買って読んでみた。筋として共通する部分はほとんどないと言っていい。落ちぶれた老セールスマンが、期待をかけた息子ともうまくいかず、起死回生で保険金目当てに自死するという悲劇だ。敗残の人間に厳しいアメリカ社会、自己欺瞞と欲、父と子、様々なテーマが折り重なって考えさせられる。しかし映画は「急速な近代化に適応できない人々が崩壊する」話ではない。
映画のラナはその夜に闖入した何者かによって乱暴されケガを負う。エマッドは怒り、警察に行こうというが、精神的にも憔悴したラマは事件を表ざたにしたくないと拒む。しかしエマッドの怒りは収まらない。傍にいて欲しいというラマをひとり置いてまで、犯人を見つけ出そうと捜索を始める。その果てに彼が見つけ出したのは意外な人物だった…。

だが映画のタイトルは「セールスマン」なのだ。「セールスマンの死」のモチーフが映画の中に潜んでいるに違いない。それはいったい何なのだろう。
映画の中で稽古として紹介される「セールスマンの死」のシーンがある。老セールスマンが若かりし頃、浮気現場を息子に見られる決定的な場面だ。以来、息子に対する負い目が消えず、それに比例するように過大な期待を寄せ、結果として息子をダメにしてゆく、その発端の事件である。老セールスマンが泊まっていたホテルを訪ねてきた息子。その時、見えない浴室から聞こえてくる女の笑い声。これが映画では後半への微妙な伏線になっている。
そして両者に伏在するのは人間の「プライド」の扱いがたさだ。老セールスマンは羽振りが良かった過去のプライドから自己欺瞞に陥り、現実を見ようとしなくなる。またエマッドは隣人たちの視線を気にして、プライドを保つために復讐せずにはいられなくなる。どちらもそのことが周囲(家族)に軋轢をもたらし、遂に破滅へと至る。

人は己の心に潜む、何か虫のようなものに縛られずにはいない生き物なのだ。それは時にプライドであり、時に憎しみであり、時に欲望であったりする。後悔はするがまた同じ虫がうごめくと同じ結果をもたらす。夫婦であっても、家族の中にいても、虫に対処するのは結局自分しかいない。虫は自分自身だから。その意味でどんなに孤独にみえなくても、人は孤独である。
監督・脚本:アスガー・ファルハディ
主演:シャハブ・ホセイニ、タラネ・アリドゥスティ
イラン・フランス 2016 / 124分
公式サイト
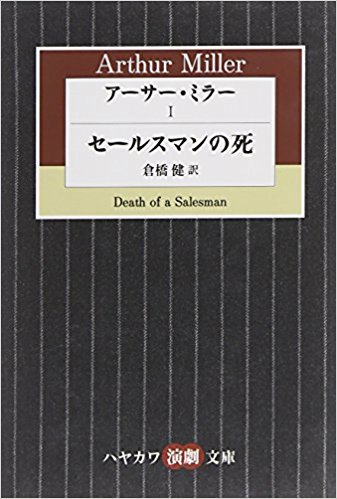
残像

ポーランド。なだらかな草原で絵を描く学生たち。そこにひとりの女学生が訪ねてくる。
「ストゥシェミンスキ教授は?」
「あそこにいますよ」
指さす方を見ると、丘の上に松葉杖をついた初老の男がいる。
「見ててごらんなさい」
男は斜面を寝転がりながら降りてくる。丘の上にいた学生たちも、それを見ると次々に寝転がって降りてくる。笑い声が草原にこだまする。訪ねてきた学生の前に立つと男は言う。
「ウッチ造形大学、ストゥシェミンスキの課外授業にようこそ!」
男はヴワディスワフ・ストゥシェミンスキ。20世紀前半に実在したポーランドの前衛画家だ。ある時、自宅でキャンバスに絵を描こうとすると、キャンバスが白から赤に変色していった。みると窓の外にスターリンの巨大な垂れ幕が掲げられようとしていたのだ。驚き怒ったストゥシェミンスキは窓を開け、垂れ幕を引き裂いてしまう。警察は即座に彼を連行してゆくが…。

監督は去年90歳で亡くなったアンジェイ・ワイダ。最後の作品である。舞台は第2次大戦後、スターリン主義が浸透していくポーランド。
「『残像』は、自分の決断を信じ、芸術にすべてをささげた、ひとりの不屈の男の肖像です。…私は、人々の生活のあらゆる面を支配しようと目論む全体主義国家と、一人の威厳ある人間との闘いを描きたかったのです。」
ストゥシェミンスキは国家の意向に沿った創作を拒否、次第にポーランドで地位を失ってゆく。どうして同じ方向に向かないのかと、当局者はいぶかる。しかし、周囲と同じ方向を向かないのが芸術家なのだから、求める方が間違っている。(日本はこれが間違いであるという社会でありつづけて欲しいが)
かつて金子光晴が書いた詩句を思いだす。
侮蔑しきったそぶりで、
ただひとり、
反対をむいてすましてるやつ。
おいら。
おつとせいのきらひなおつとせい。
だが、やっぱりおつとせいはおつとせいで
ただ
「むかうむきになつてる
おつとせい」

さらに間違っているのは同じ方向を向かない人間、「むかうむき」の人間を迫害することだ。ストゥシェミンスキは大学での職を失い、信奉する学生のあっせんでようやく得た看板描きの仕事も取り上げられてしまう。そしてついには、食べることもままならず、飢えから皿をなめるようにまでなるのだ。
当局に「あなたはどちら側なのだ」と問われたとき、ストゥシェミンスキは即座にこう答える。
「私の側だ」
そして歩き去りながら、再び自らに確認するようにつぶやく。
「自分の側なんだよ」
ストゥシェミンスキは、苦境に陥っても少しも妥協しない。彼を助ける女学生が捕まり、協力しなければ彼女を「痛めつける」と脅されても決して意思を曲げることがない。この世界で彼は敗北者である。しかしワイダは一貫しておのれの理想に殉じる敗北者を描いてきた。それは決して人生の敗北ではないという意思を込めて。

彼が学生たちに教える絵画理論にこういうものがある。
「人は認識したものしか見ていない」
ということは、認識せずに見ていないものがある、ということだ。勝手に解釈すれば、見ていない世界になにがしかの真実が隠れているかもしれず、そのことに少しは思いをはせるべきだと語っているのだ。そして社会というものもそうなのだ、と。
「一人の人間がどのように国家機構に抵抗するのか。表現の自由を得るために、どれだけの対価を払わなければならないのか。全体主義国家で個人はどのような選択を迫られるのか。これらは過去の問題と思われていましたが、今もゆっくりと私たちを苦しめ始めています。」
遺作「残像」に寄せたコメントでワイダはこう語り、次のように続く。やはり、遺言というべきものだと思う。
「どのような答えを出すべきか、私たちはすでに知っている。そのことを忘れてはならないのです。」
監督・脚本:アンジェイ・ワイダ
主演:ボグスワフ・リンダ、ゾフィア・ヴィフワチ
ポーランド映画 2016 / 99分
公式サイト
光

ある会議室。モニターを見ながら映像を言葉にして語る女性、尾崎美佐子。目の見えない人に映画を楽しんでもらうための音声ガイドだ。映画が終わると、その場にいた視覚障がいを持つ人たちが、ガイドの内容について意見を言う。目が見えない立場で、映画を楽しめたかどうか、表現は適切か、など口々に指摘する。ボランティアで行う音声ガイドに対する遠慮からか、当たり障りのない言葉が続く中、ある男だけが厳しく言い放つ。
「今回のガイドは、今のままだと邪魔なだけです」
美佐子のガイドは意見の押し付けだという。男は中森雅哉。元は知られたカメラマンだったが、徐々に視力を失いつつある。言葉の激しさに戸惑い、怒りさえ覚える美佐子だったが…。
「『あん』のときに音声ガイドを制作して、初めて今作のモチーフになっている世界に触れたのですが、音声ガイドの皆さんの映画への愛に本当に感動したんですよ。その愛で、目の不自由な人たちに映画を届けようとしていて。私は、そういう愛を持って誰かとコネクトしていこうとする人たちの物語を作りたい。」(シンラネットインタビュー)

映画は劇中でもう一つの映画を新撮している。「その砂の行方」という作品だ。認知症の妻をもつ年老いた男が、ラストで砂浜をさ迷い歩く。音声ガイドの美佐子はそのラストで映像をこうガイドする。
「重三の顔は希望に満ちている」
中森が美佐子のガイドで特に引っかかっていたのは、このラストシーンだ。後日、美佐子が自分のガイドについて意見を聞きたいと監督を訪ねるシーンがある。監督はその個所を読んで少し考え込んでしまう。
「あのね、重三はもう死ぬかもしれないんだよ。そういう年齢なんだ。死ぬかもしれないし、まだ死なないかもしれない…」
すると美佐子が強い口調で言い返す。
「そんなあやふやなものじゃなくて、映画はもっとはっきりした希望が必要なんです」
少し驚く監督。助監督が休憩時間の終わりを告げる。立ち上がりながら監督は言う。
「この映画が君の希望になったことをうれしく思うよ」
美佐子の父親は失踪しており、認知症の母親が田舎でサポートを受けながらひとり暮らしをしている。この映画は「希望」について語ろうとしているのだ。

映画は美佐子がこのラストシーンをどうガイドするのかを縦軸に、元カメラマン中森との交流を横軸に進む。中森の絶望は深い。視覚を失う中で、生きる証のようなカメラマンという職業を捨てなければならないのだ。
演じる永瀬正敏は、映画からは本来感じ取れない、視覚と聴覚以外の感覚、つまり匂いや体温、息遣いなど人間の生理に由来するものを感じさせる。永瀬の演技によるものなのか、タイトなカメラワークによるものなのか、両方なのか。とにかく永瀬の中森のおかげで、この作品は不思議ななまもののような映画になっている。

加えて作品中にあふれる光。河瀬監督は舞台あいさつで
「世界に存在する愛とか光とかを全部集めて刻みたかった」
と話したという。しかし、映画が語る希望は「光」にあるのではない。闇に閉ざされようとする中森にとって光は希望ではない。
白杖をつきながら美佐子に向かってふらふら歩く中森の足元、崩れる砂浜を一歩一歩踏みしめる劇中映画の重三の足元、かろうじて踏み出すそのわずかな一歩に、希望はあると思える。
そして映画は私たちに、こう問いかけているのだ。
「あなたにとって、いやむしろあなたの隣にいる人にとって、希望とは何ですか」
と。

夜空はいつでも最高密度の青色だ

青森だったか、在来線の列車の窓から夕暮れの空を眺めていた。白い雪原の上の空はよく晴れ渡り、青色は時間がたつにつれてどんどん濃くなってゆく。このタイトルを見て思い出したのはその光景だった。青と黒のグラデーションはとても幻想的だったが、駅に着いたとたん、制服の中学生たちの喧騒に紛れた。
東京。ある病院で看護師として働く美香。幼い子どもを2人おいて亡くなった病人がいる。泣き崩れる夫。それを見つめながら美香はそっとつぶやく。
「大丈夫。すぐ忘れるから。」
建設現場で働く慎二。彼の見る風景は左半分がない。左目がほとんど見えない。なぜか何か意味のないことを喋らずにはいられない。仲間からはいつも「うるせー」と怒鳴られる。映画は美香と慎二が偶然出会うところから始まる。

脚本・監督は石井裕也。最果タヒの同名の詩集「夜空はいつでも最高密度の青色だ」を元に作った。詩集が原作という珍しい作品だ。
「最果タヒさんは現代の、特に都市に生きている人の心情とか気分みたいなもの、言葉にならない感覚を言葉によってつかもうとしているというか。いま都市で生きている、特に若い人たちの何かに触れようとしている詩集だと僕は思っていて。」
映画のタイトル(詩集のタイトルでもある)の詩句を含む「青色の詩」。
都会を好きになった瞬間、自殺したようなものだよ。
塗った爪の色を、きみの体の内側に探したってみつかりやしない。
夜空はいつでも最高密度の青色だ。
きみがかわいそうだと思っているきみ自身を、誰も愛さない間、
きみはきっと世界を嫌いでいい。
そしてだからこそ、この星に、恋愛なんてものはない。
映画は東京という町にこだわる。東京は単純に人が多い。うるさい。なぜ東京にいるんだろうという問いは、なぜ生まれて来たんだろうっていう問いと同じ。美香と慎二はいつも嫌な予感を抱えている。あらゆる問いが、答えにならない答えを伴って空を舞っている。

「ねぇ、恋愛すると人間が凡庸になるって本当かな」
と美香が何度も問いかける。
「さあ」
凡庸なのは恋愛しないからだ、といういい方もできる。凡庸が悪だなんて誰が言ったんだろう。美香が失意にある時、慎二が「できることは何でも言って」という。すると美香が言う。「死ねばいいのに」。
最果タヒの詩句にある。
死ね、といえば簡単に、孤独を手に入れられていた。
(「ゆめかわいいは死後の色」)
慎二は「死ぬ」という言葉を嫌う。しかしここでは何も言わない。自分の「死」だからか。凡庸が嫌いな人間が、「孤独」を手に入れるために言葉で人を傷つける。美香は何かに傷ついているのだろうけれど、とてもめんどうくさい人である。しかし、慎二は惚れてしまう。とてもやさしい人である。
孤独になれば、特別になれると、思い込むぼくらは平凡だ。制服がかろうじてぼくらを意味のあるものにしてくれる。
(「かわいい平凡」)
慎二は美香の田舎で夜中に自転車をこぐ。美香を乗せて。街灯もない真っ暗な闇だ。東京には「黒」がないという美香。世界の半分しか見えないという慎二は、美香の背負うものをすべて半分にしてあげる、という…。肉体性を感じない、とても観念的な恋愛映画と言えなくもないのだが、そうならざるを得ないのが「いま」なのか。

青森で見た夕暮れの青色は、だんだん濃くなってゆくとやがて黒一色の夜になる。最高密度の青色は夕暮れから夜に変わる、その一瞬だ。その一瞬をとらえることが難しいので私たちは、東京の空をついに見上げることがない。
マンチェスター・バイ・ザ・シー

ボストン郊外。アパートの玄関先で雪かきをしている男。名前はリー。アパートの便利屋で、下水管の詰まりや浴室の水漏れを修理する。仕事を黙々とこなすが愛想が悪い。気に入らないことがあると住民を口汚く罵っては苦情がくる。酒を飲んでは喧嘩。同じ毎日の繰り返し。
そんなある日、兄のジョーが倒れたという知らせを受け、マンチェスター・バイ・ザ・シーに向かう。生まれ故郷の小さな海沿いの街だ。病院に着くとすでに兄は亡くなっていた。ジョーには一人息子で高校生のパトリックがいる。兄の遺言は、リーにこの町に戻って後見人になって欲しいという。しかし、リーにはこの町に住めない理由があり、パトリックをボストンに連れて行こうとするのだが…。
監督・脚本はケネス・ロナーガン。劇作家として活躍し長編監督は3作目。マンチェスター・バイ・ザ・シーは、元はマンチェスターという地名だったが、他のマンチェスターと混同しないように、30年近く前に改名されたという。
「美しさとわびしさを感じる場所だ。おもしろいことに、町自体は裕福なボストン人のリゾート地なのだけど、ブルーカラーの人々がボートのサービスなどで、休暇で訪れる人々をサポートしている。…実生活と自然の美しさが混在する町だ。」

いくつものヨット。煙突のあるカラフルな家々。しかし冬のこの町で空はいつも鈍色をしている。地面も凍って埋葬は春まで待たなければならない。甥のパトリックは彼の日常が続く。ガールフレンドに二股をかけ、バンド活動、アイスホッケー…。どこに行くにもリーが送り迎えをする。ある時彼女のひとりサンディーと部屋で二人きりになる時間を稼ぐため、彼女の母親と話をしてくれと頼まれる。30分でいいから、と。しかしリーはその30分がもたない。
「叔父さんは普通の世間話ができないの?」
と甥になじられる始末。映画は甥との日々の中に、かつてこの町で暮らしていたリーの日々が挟み込まれる。遺言を預かった弁護士が言う。
「リー、君の経験は創造を絶する。後見人になりたくないなら君の自由だ」
そしてリーの過去に何があったのかが明かされる。

「リーは、自らの身に起きた悲劇をきっかけに、世界が灰色になってしまったと感じている。だが、どんなにひどい不幸を体験しても、世界が灰色になることはない。なぜなら、人間は一人で生きているわけではなく、常に周囲でさまざまな興味深いことが起きているからだ。」(ケネス・ロナーガン監督)
兄が遺した一隻のボートはモーターがすでにいかれていた。リーの発案でようやくモーターを買うことができたパトリックは、彼女のひとりサンディーを乗せて海に出る。彼女に運転を任せるが、船が大きく旋回する。悲鳴が上がる。慌てることはない、舵をまっすぐにするだけだと教える。大きく旋回を続ける船の縁に腰かけたリーが大きく笑う。リーの背後でヨットハーバーが回ってゆく。めまいがする。
しかし同じ日、リーは町中で偶然、元妻のランディーと再会してしまう。
「あの時、私の心は壊れたの。あなたの心も。そして今もそのまま…」

再び大きく心がかきむしられる。記憶が消えてゆかない。狂い始める。酒を飲む。けんかをせずにはいられなくなる。人は何のために生きるのか。生き続けるのか。死に向かう心をかろうじて思いとどまらせるものは何なのか。
自分が苦しいとき、世界がまったく無関係に動いている。そのことに苛立ち、腹立ち、羨望せずにはいられない。しかし同時に、たった一人愛する人が、まったく別の世界で生きているという希望が、自身の足元をかすかに照らすこともある。海沿いの街の、鈍色の空からふるやわらかな光のように。

監督・脚本:ケネス・ロナーガン
主演:ケイシ―・アフレック、ミッシェル・ウィリアムズ、ルーカズ・ヘッジズ
アメリカ映画 2016 / 137分
公式サイト
草原の河

チベット。標高3000メートルを超える高地に、羊を放牧して暮らす人々がいる。まだ春浅い日に、グルの一家は村を出て放牧のためのキャンプ地に移り住んだ。乾いた風が吹きつのり、強い日差しが肌を灼く。時折降る雪まじりの雨。家族は妻のルクドルと6歳の娘ヤンチェン・ラモ。
夜中に羊が騒ぎ目を覚ます。オオカミが羊を襲うのだ。ケガをした羊をテントに入れるが、翌朝には死んでしまう。死んだ羊の子どもなのか、子羊がテントの周りをぐるぐる回る。ヤンチェン・ラモは、その羊にミルクをあげジャチャと呼んで可愛がる。とてもシンプルな生活だ。
しかし、母親が妊娠したことで、ヤンチェン・ラモの思いは複雑だ。お気に入りのクマのぬいぐるみを、生まれてくるあかちゃんにあげなければいけないかもしれない。父親が「天珠」を見つけたから子が授かったと母親に聞いたヤンチェン・ラモは、その天珠を土の中に隠してしまうのだが…。

監督・脚本は、青海省のチベット族自治州生まれのソンタルジャ。長編二作目。親戚のヤンチェン・ラモに出会い、彼女を同名の主人公に撮影しながら物語を紡ぎ出したという。
「私は失われたものを描きたくてこの映画を撮ったわけではない。急激な発展によって失ったものは世界中にたくさんあるが、そんな中で人間はどう生きているのか。それはチベットも世界の他の地域も何ら変わりがないということを言いたかった。」
はるかに続く草原には、放牧される羊と3人の家族以外に何もない。グルの移動手段はバイクだ。娘のヤンチェン・ラモを連れて、村人から“行者さま”と呼ばれる父親のもとへ病気見舞いに行く。道中を遮るのは、河だ。暖かくなって氷が解け、バイクを落としてしまう。苦労の末ようやくたどり着いても、グルは父親には会わず、ヤンチェン・ラモだけにあいさつさせる。父親とは何かの理由で会うのを拒んでいるのだ。

父親は文革で一度は僧侶をやめさせられ、その時妻をめとりグルが生まれたが、文革が終わると家族を捨てて僧侶に戻っていったらしい。映画はこのグルと父親との確執、そしてヤンチェン・ラモとやがて生まれてくる赤ちゃんとの関係を軸に進む。それはここがチベットであろうがどこであろうが普遍的なものだ。しかし生活の単純さは、思いの一つ一つを深く長くする。
「私にとって映画を撮る意味は、自分とは何者なのかということを探し続けることなのです。チベットにはまだまだたくさんの物語がある。」(ソンタルジャ監督)
物語の終盤、やがて放牧の季節が終わろうとするころ、河が増水し行く手を阻む。しかし同じ岸辺にいる者たちは、河の前に佇み時を過ごすことができる。そして思いを共有する。

河は人を隔て、人を繋げる。そのような土地にヤンチェン・ラモは暮らし、やがて何ものかを残して生を終える。
監督・脚本:ソンタルジャ
主演:ヤンチェン・ラモ、グル・ツェテン、ルンゼン・ドルマ
原題:河 中国映画 2015 / 98分
公式サイト
ぼくと魔法の言葉たち

アメリカ、マサチューセッツ州。プライベートなホームビデオが映し出される。ありふれた親子。しかし…。
3歳になる頃 オーウェンは突然消えた
自閉症だと医者は言った
一生話せないかもしれない、と医者は続ける。失意の家族。しかし転機は6歳の時に訪れる。オーウェンの発する言葉が、いつも見ているディズニーのセリフかも知れないと両親が気づいたのだ。これは、ディズニーアニメによって言葉を取り戻したオーウェン・サスカインドの、今を追ったドキュメンタリーである。

6歳の時、父親のロンがディズニーのキャラクターになりきって、彼に声をかけてみる話は感動的だ。オーウェンのお気に入りは、「アラジン」に出てくるオウムのイアーゴ。この時までほとんど言葉を発しなかったオーウェンに、ロンは声色を真似て背後から近づく。そして聞いてみる。
「君でいるのって、どういう気分?」
すると、オーウェンがきちんと答えたのだ。
「つまらないよ。友達がいないから。」
監督は、TVプロデューサーでありドキュメンタリー作家のロジャー・ウィリアムズ。
「ゲイの黒人である私自身もはみ出し者であると感じているので、世の中の声なき人たちに声を与えたいと考えてきました。そして私たちみんなが共に暮らし、互いを理解し合える方法を見つける努力を続けてきました。」

オーウェンから世界はどのようにみえるのか。映画は音と映像を駆使し、彼の内面世界を描こうとする。彼に聞こえているであろう外界の音を作り出し、彼が考えた独自の物語はアニメ化して見せる。監督とサスカインド一家はもともと知り合いだったという。制作には2年の歳月をかけた。
「正直に言えば、自閉症の人たちに対して、少し恐れを抱いていました。どのように触れ合い、コミュニケーションを取ればいいかが分からなかったからです。しかしこの作品のお陰で自閉症への考え方が完全に変わりました。自閉症が欠点や障害であるという見方はなくなり、相違点だと思うようになりました。」
オーウェンとわれわれは違う。明らかに違う点がある。ただし、「われわれ」の、我とあなたも違う。同じように明らかに違う点がある。私以外の人が私と違うことに苛立ったり、怒ったりしても詮無いことである。厳密な意味で「普通の人」というのは存在しないのだ。だとすれば人間の社会というのは、違いを許容しない限りお互いにとても生きづらいものだと思う。

オーウェンは成長し、両親のもとを離れる。映画はその後を追いかけ、誰にも訪れる青春の試練、すなわち「失恋」がオーウェンにも訪れるさまを記録する。ディズニーでその試練を乗り切ることができるか、私たちはハラハラドキドキしながら見守ることになる。
それにしてもオーウェンの、失恋相手に対する自制心に満ちた態度には驚かされる。自閉症は対人コミュニケーションに難があるという。しかしこういう時の絶望の深さに違いはなかろうに、強いひとである。

監督:ロジャー・ロス・ウィリアムズ
原作:「ディズニー・セラピー 自閉症のわが子が教えてくれたこと」(ビジネス社)
アメリカ 2016 / 91分
公式サイト