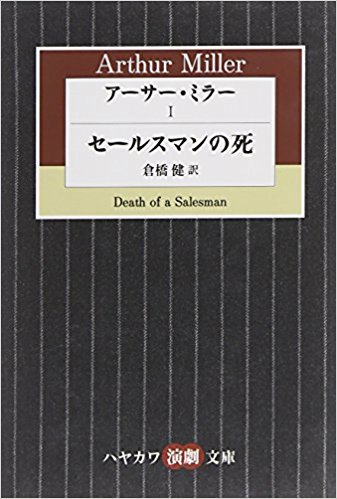セールスマン

暗闇にうかびあがるベッド。照明を移動させる音。次にソファ。そして正面に派手なネオン看板。これは演劇の舞台だ。しかし人はいない。
一転して叫び声。ドヤドヤと階段を駆け下る音。アパートが倒壊しそうだという。これは現実だ。主人公らしき男が、助けの必要な隣人を抱えて降りてゆく。窓にひびが入る。外にはブルドーザーがうなりをあげている。
イランの首都テヘラン。乱開発のひずみで住む場所を失ったエマッドと妻のラナは、ともに舞台俳優だ。稽古中の舞台はアメリカの劇作家アーサー・ミラーの「セールスマンの死」。劇団仲間が紹介してくれたアパートに急いで引っ越した二人だったが、ある夜、ラナは呼び鈴を夫のものと勘違いし、見知らぬ他人にドアを開けてしまう…。
監督・脚本は「別離」が世界的にヒットした、イランのアスガ―・ファルハディ。
「私は学生の時に、「セールスマンの死」を読み、とても胸を打たれました。…とても重要なポイントは、都会であるアメリカの突然の変化によって、ある社会階級が崩壊していく時代の社会批判です。急速な近代化に適応できない人々が崩壊するのです。その意味で、この戯曲は、私の国イランの現在の状況をうまく捉えています。」

映画を観た後、パンフレットに並べて売られていた「セールスマンの死」の文庫本を買って読んでみた。筋として共通する部分はほとんどないと言っていい。落ちぶれた老セールスマンが、期待をかけた息子ともうまくいかず、起死回生で保険金目当てに自死するという悲劇だ。敗残の人間に厳しいアメリカ社会、自己欺瞞と欲、父と子、様々なテーマが折り重なって考えさせられる。しかし映画は「急速な近代化に適応できない人々が崩壊する」話ではない。
映画のラナはその夜に闖入した何者かによって乱暴されケガを負う。エマッドは怒り、警察に行こうというが、精神的にも憔悴したラマは事件を表ざたにしたくないと拒む。しかしエマッドの怒りは収まらない。傍にいて欲しいというラマをひとり置いてまで、犯人を見つけ出そうと捜索を始める。その果てに彼が見つけ出したのは意外な人物だった…。

だが映画のタイトルは「セールスマン」なのだ。「セールスマンの死」のモチーフが映画の中に潜んでいるに違いない。それはいったい何なのだろう。
映画の中で稽古として紹介される「セールスマンの死」のシーンがある。老セールスマンが若かりし頃、浮気現場を息子に見られる決定的な場面だ。以来、息子に対する負い目が消えず、それに比例するように過大な期待を寄せ、結果として息子をダメにしてゆく、その発端の事件である。老セールスマンが泊まっていたホテルを訪ねてきた息子。その時、見えない浴室から聞こえてくる女の笑い声。これが映画では後半への微妙な伏線になっている。
そして両者に伏在するのは人間の「プライド」の扱いがたさだ。老セールスマンは羽振りが良かった過去のプライドから自己欺瞞に陥り、現実を見ようとしなくなる。またエマッドは隣人たちの視線を気にして、プライドを保つために復讐せずにはいられなくなる。どちらもそのことが周囲(家族)に軋轢をもたらし、遂に破滅へと至る。

人は己の心に潜む、何か虫のようなものに縛られずにはいない生き物なのだ。それは時にプライドであり、時に憎しみであり、時に欲望であったりする。後悔はするがまた同じ虫がうごめくと同じ結果をもたらす。夫婦であっても、家族の中にいても、虫に対処するのは結局自分しかいない。虫は自分自身だから。その意味でどんなに孤独にみえなくても、人は孤独である。
監督・脚本:アスガー・ファルハディ
主演:シャハブ・ホセイニ、タラネ・アリドゥスティ
イラン・フランス 2016 / 124分
公式サイト